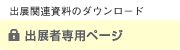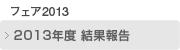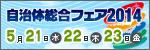日本には大変優れたモノ作り中小企業がたくさんある。これらは大きく分けて3つのタイプがある。一つ目は自動車産業などのサプライチェーンに組み込まれている、いわゆる下請企業のように、大手企業と安定した取引をしているような企業である。大変優れた技術力があるが、中核となる取引先企業の事業所、工場が海外に移転すると一緒に出ていかざるを得ないという事情があり、国内に立地することよりは海外立地に頭を悩ませている企業が多い。
2番目のタイプは、大田区や東大阪などにある加工サービス、とくに鍛造であるとか鋳造、切削、メッキ、熱処理、表面処理といった特定分野の単工程の加工サービスを提供している非常に零細だが高い技術力を持っている企業である。これらの企業には二通りのタイプがあり、一方はニッチトップ (NT) 型の企業を目指してさらに発展しようという企業、他方は経営者が高齢化し後継者がなかなか見つからないため、むしろ廃業が検討されているような企業である。大田区や東大阪の事業所数が減っているのは、将来の事業継続に望みが持てないがために廃業していくといった人たちが多いことによる。
3番目がグローバルに活躍しているNT型企業でグローバル・ニッチトップ (GNT) 企業という。独自製品を供給するタイプと、他社が真似のできない高度な加工サービスを提供するタイプがある。製品であれば特定の分野で極めて競争力の高い製品を作っており、特定の顧客への依存度が低く、取引先も多く、独立性が極めて高い企業である。また、こういった企業の中でとくに優れた企業は国際競争力があるため、価格が多少高くても日本で作り、日本から海外に輸出することができる。すなわち、円高、人件費高、電力料金高を乗り越え、日本を主な活動場所として、日本で生産し輸出することができる非価格競争力を持った企業である。
GNT企業の特徴の一つは全国に分布しているということである。もちろん大都市地域に多いのだが、北海道から九州に至るまで全国に分布している。とくに地方に本社が所在しているこのタイプの企業は、地元では非常に有名な企業であり、その地域を代表する企業である。
GNT企業の特徴の二つ目は、競争力が強く海外へ自然と浸透していけるだけの力を持っていることである。GNT企業は、これからも日本で、ものづくりを続けていこうという意欲と能力に富んだ中小企業である。こういう企業の中には、現在の立地場所では手狭であり、事業を拡張するといった観点から新しい適地を探しているような企業や、将来の大災害に備えて立地場所を移したいと考えている企業もある。
2011年、全国の代表的なNT型企業31社にヒアリング調査を行った。どのような企業を調査したかというイメージを持っていただくために具体的な例を挙げてみる。大阪の中心、北区堂島に本社を置く利昌工業(株)という企業がある。調査を実施した中では企業規模が最も大きい方で従業者数は500人である。
同社はプラスチックカードとICチップの間に入れるガラスエポキシ樹脂テープを作っている。ガラスエポキシ樹脂はガラス繊維の中にエポキシ樹脂という熱や圧力に強く導電性のある樹脂を含浸させて、何層にも重ねたものであり、プラスチックカードとICチップを圧着する過程で必ず必要となるものである。利昌工業は、自動で圧着を行えるよう個々のガラスエポキシ樹脂を一定の間隔でテープの上に載せ、供給している。ICカードは日本で普及するよりも遥か以前、1980年代の初めにヨーロッパでテレフォンカードとして普及した。そのため今でもICカードはヨーロッパが一番進んでおり、日本は加工されたICカードをヨーロッパから輸入している。利昌工業は、フランスの大手ICカードメーカーが自社の工場敷地内に工場用地を確保し、買い取りも100%保証するから、という条件でフランスに来てくれという要請を断っている。なぜなら海外へ出ていけば技術の漏出は避けらないと考え、それを嫌ってあくまで日本で作り続けている。利昌工業のシェアは85%である。これがGNT企業の典型的なタイプであり、こうした企業はさまざまな理由で、むしろ日本に留まる必要を感じている。
最近の風潮は官民挙げて、海外へ出ていこう、国をあげてそれを支援しようという傾向が強い。こうした中で、今日お集まりの皆さんには、海外進出に慎重でありながら非常に優れた企業が日本にはまだまだあるのだということを認識していただきたい。
GNT企業を増やしていくこと、GNT企業にさらに飛躍していただくことを目的に、既にここ15年ほど国も政策を打ってきた。最初が1999年制定の新事業創出促進法に基づく地域プラットフォーム事業で、中核的支援機関を全都道府県と政令市に設け、研究開発から販路開拓まで一貫して支援するというものであった。2001年から“産業クラスター計画”が始まった。目標は、世界に通用する国際競争力を有する産業・企業を創出するということであり、まさにグローバルに活躍するモノ作り企業、とくに中小企業の支援ということが主要な目的であった。2006年からは中小企業庁がこういうタイプの企業を公表し、これらの企業に注目が集まるようにしたり、さらなる発展を促そうと、「元気なモノ作り中小企業300社」という顕彰事業を始めた。4年間続けられ、1,200社が選ばれている。
2011年に日本全国から代表的な企業31社を選び、それぞれ2時間ぐらいかけてインタビュー調査を行った。その結果、いくつかの非常に重要な共通点が明らかになった。共通点の1番目は、製品開発においてニーズを掴まえる能力が極めて高いということである。近年、自治体等の支援機関で、中小企業のニーズで最も大きいのは販路開拓である。それは、製品を開発したものの販路開拓で行き詰る企業が多いことを示している。こうした企業がどのようなやり方で製品を開発しているかというと、自社が保有している技術等シーズから発想しニーズを考慮していないため、一から販売先を開拓しなければならず、結局売れないで困ってしまう。これに対して、成功しているNT型企業はニーズを掴まえることにおいて非常に優れた能力を持っており、ニーズに基づき製品を開発するので、販路は自ずと開けてくる。では、どうやってニーズを掴まえるのか? こういったタイプの企業は、問題解決(ソリューション)能力が高いといった評判を何らかの形ですでに確立している場合が多く、「こんなことで困っているのだが何とかならないか」とか「こんな製品が欲しいが、お宅ならできるのではないか」という形で、ユーザーの方からニーズを持ち込んできてくれるのである。
2番目の重要な共通点は、そういったニーズが持ち込まれると必ずソリューションを出すということである。「分かりました。ちょっと預からせてください」と言って、ニーズを断ることはしない。その代わり、石に噛りついてでもソリューションを出そうと必死に努力する。しかし、規模の小さな中小企業なので、自社の中だけで解決できることばかりではない。日頃から自分の周りに独自のネットワークを築いていて、ソリューションを出すために必要な外部資源の活用に非常に長けている、というのが特徴である。すなわち、自分がソリューションを出すために必要とされるさまざまな技術とか、情報とかを提供してくれる応援団、一緒になって開発に協力してくれる企業や大学の研究者の人たちとのネットワークを構築しており、いざという時にそれをフルに活用できるという優れた能力を有している。
共通点の3番目は、先に利昌工業の例で述べたように模倣を防ぐ、真似をされないように細心の注意を払っているということである。模倣防止というとすぐに特許を思い出す。確かに特許も重要だが、特許だけで守りきれるというのはむしろ非常に珍しいケースである。
31社の中に根本特殊化学(株)という夜光塗料のメーカーがある。昔、夜光塗料は発光のエネルギー源として放射性物質を使っていた。この企業は、放射性物質フリーの新しい夜光塗料を開発した。蛍光灯は、いくつかの有色発光体を組み合わせて白色を出している。昔は消してもボーと光が残った。これは緑の色を出す発光体の蓄光能力が原因であった。蛍光灯メーカーは残光を一生懸命消そうと改良に熱心に取り組んだ。同社はその逆手を取って、緑の発光体の蓄光能力を最大限に引き出す方向で研究開発を行い、放射性物質を使わないN夜光という製品の開発に成功する。この製品の特許は物質特許であり、組成が同じ製品は特許侵害で訴えることができ、20年間は完全に守られる。唯一、中国だけは特許が認められず中国市場ではコピー製品が出ている。ただし、それ以外の地域では特許が取れており、中国から第三国に輸出された瞬間に訴訟を起こすことで模倣品の排除ができる。しかし、こういった例は極めて例外的であり、ほとんどの場合は特許だけでは守りきれないため、トレードシークレット、企業秘密という形で、様々な工夫をして一生懸命守っている。「外国に出ていかない」という利昌工業のやり方もそうした工夫の一つであり、他にもありとあらゆる手段を尽くして真似をされない努力をしている。利昌工業は、工場の重要な工程は自社の営業マンにも見せないようにしている。
4番目の共通の特徴は、非常に高い国際競争力があるため無理に海外へ出ていく必要がないという点がある。海外へ出ていくのに慎重すぎるくらい慎重な企業が少なくない。
電子線描画装置という半導体製造装置の一種を作っている(株)エリオニクスという企業がある。同社は、昨年、世界のコンペティターとの競争を制し、アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)に自社製品が採用された。そんな優秀な製品を作っているのに、今のところヨーロッパには輸出していない。なぜかというと、同社の製品はメンテナンスが必要で、いつでも顧客のところに飛んでいける体制を確保しておかなければならない。そうした準備がない段階で「ヨーロッパに下手に輸出したら評判を落とすから輸出しない」と言うのである。
大体、こういうタイプの企業の海外展開は輸出から始まるのだがアフターサービスが必要な場合が多く、海外にメンテナンス拠点やメンテナンスを請け負ってくれる代理店を設けなければならない。エリオニクスは、日本の大手電子顕微鏡メーカーから独立創業した経緯がある。この日本の大手メーカーと覇を競いあった米国の電子顕微鏡メーカーの社員だった人が起こした企業に代理店を依頼している。そして、その企業の社員を受け入れ、メンテナンスのための研修を施し、アメリカに戻しているためアメリカには輸出できる。このように、GNT企業の国際展開は、輸出がまずあって、そのためのメンテナンス拠点、アフターサービス拠点から入り、その次に販売拠点、さらに生産拠点と、段階を踏んで必要に応じて行われることが多い。
こうしたヒアリング調査に引き続き、2012年、独立行政法人経済産業研究所のプロジェクト「優れた中小企業(Excellent SMEs)の経営戦略と外部環境との相互作用に関する研究」の一環としてアンケート調査を実施、調査結果を2013年3月に発表した。アンケート記入に1時間以上かかる、極めて記入負担の重い調査であった。簡単なアンケート調査でも回収率がなかなか上がらないのが普通なのに、これだけ記入に手間の掛かる調査にもかかわらず2,000社のうちの1/3、663社から回答を得ることができた。主要なファクトファインディングを紹介する。
まず、NT型の企業は社歴が長く、非常に古い企業が多いということである。従業者数は平均97人、年間の売上高は平均で23.5億円であり、中小企業の中ではかなり規模が大きい。
2,000社とは別に一般の中小企業1,000社についても民間企業データベースからランダムに抽出して調査している。ランダムサンプル企業の回収率は17.8%であり、従業者数39人、売上高8.8億円となっている。NT型企業の規模の大きさが分かる。
一方、経常利益率は、NT型企業の利益率が直近で5.7%、リーマンショック前では7.7%と高く、大企業でもこれより低い企業はいくらでも存在する。
従来から経験則として、従業者一人当たりの売上高が2,000万円、というのが優良なものづくり中小企業の目安だと言われている。今回のアンケート調査で、NT型企業の従業者一人当たりの売上高は約2,000万円ということになっており、ここからもNT型企業が、中小企業の中でも優れていることが分かる。
もう一つ重要な発見は、このNT型企業の中でもとくに良いパフォーマンスをあげている企業の存在が明らかとなったことである。それはGNT企業である。アンケート調査の具体的で数値で、GNT企業がとくに優れていることがはっきり示されたのは極めて重要な点である。GNT企業の定義は、今回、NT製品を複数持っており、かつ海外市場でもシェアが立っていることとした。NT製品が一つだけでは一発屋で終わっている可能性があるので、二つ以上持っているということを優れたNT型企業の条件の一つとした。海外市場でもシェアを得ているという条件は、グローバルに活躍していることを示す。ここでは、シェアは何%ということは問うておらず、ともかく海外で売り上げがあり、「コンペティターもいるけれどそれなりに国際市場でやっていっている」という自覚を持っているかというのが二つ目の条件である。この2条件でくくると、663社のうちの112の企業が該当し、数字から明らかにパフォーマンスが良いことが分かる。社歴はNT型企業の平均よりもさらに古く、平均従業者数は111人、売上高27.6億円、従業者一人当たり売上高2,170万円、利益率などもNT型企業の平均より上である。いろいろな分析を通じ、国際的に通用している、国際的な競争に晒されているタイプのNT型企業、つまりGNT企業があらゆる面で優れているということが今回の調査で判明した。
もう一つ今回の調査の大きな発見は、GNT企業には至っていないがGNT企業を目指している企業で、何事についても積極的な企業が存在しているということである。アンケート調査では、三つの中小企業施策の利用状況とその効果を尋ねている。一つは技術開発の補助金、公募事業に応募して採択されたことがあるかどうか、二つ目が中小企業に経営改善等の計画を作らせてその計画を国・自治体が認めた場合には法律に定めた特別の支援措置を受けられるといった法律上の認定を受けたことがあるかどうか、三つ目が「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれたことがあるかどうか、である。
この3施策を全て使っている企業を、3施策揃い踏みの企業ということで、<揃い踏み企業>と名付けた。このような企業が663社のうち205社と1/3ほどを占めている。従業者数、売上高、一人当たり売上高、利益率ともに平均を下回っているのだが驚くべきことがいくつかある。
まず一つは、足りない技術のもっとも重要な入手先として“大学等研究機関”を挙げた割合が<揃い踏み企業>では31.0%であり、一方、GNT企業は平均を下回って9.8%であった。GNT企業は大学を自社にとって利用価値があるかどうかという観点から客観的に見られるだけの優れた見識を持っており、必要な限りにおいて活用している。そのため、大学も、他の外部資源とともに相対化して見ているため、この数値がむしろ平均以下になっていると考えられる。その分、GNT企業は大企業ユーザー企業や中小の加工事業者等日頃付き合いのある企業との連携に重きをおく傾向がある。これに対して、揃い踏み企業の場合は、大学との産学連携にものすごく熱心である。
補助金の採択実績のある企業で、選択肢中最多の4回以上という採択実績があるという企業の割合は、GNT企業が40.8%、<揃い踏み企業>が40.5%とほとんど変わりはない。揃い踏み企業は、施策活用に極めて熱心である。
こうしたことから、<揃い踏み企業>は、ありとあらゆる外部資源を貪欲に使い、とにかく頑張って成功したいという意欲の高い企業であることが分かる。
ところが海外売上高比率が10%未満の企業、つまり輸出をあまりしていない企業の割合を見てみると、NT型企業の平均が69.4%なのに対してGNT企業は45.1%と予想通り低い。一方、<揃い踏み企業>は75.5%であった。つまり75.5%もの企業の海外売上高比率が10%未満というわけで、揃い踏み企業には基本的にドメスティックで、輸出がまだまだ少ないのである。NT型企業の1/3を占める企業で、国の施策も一番良く利用しており、大学にも熱心に通っている。だがパフォーマンスでみるとGNT企業にはなりきれていない、グローバル化できていない、という企業がこれだけ存在している。
立派な企業とそうでない企業をどのようにして見分けるかという、いわゆる「目利き」は極めて重要である。地域の金融機関は融資先の選定に常に腐心している。今日お集まりの皆さんも企業誘致を企業に働きかける場合、優れた中小企業に的を絞れれば、さまざまな面でメリットがあることと思う。そこで、今回の一連の調査から、ものづくり中小企業の中でこの企業は優れていると判断する基準として、どのようなものが考えられるか最後に紹介することとしたい。
その1−競争力のある自社製品をもっている
競争力のある自社製品や他社にできない高度な加工サービスを提供しているかどうかということである。「元気なモノ作り中小企業300社」に入っている企業であれば、この条件はクリアできていると考えて間違いが無い。しかし、300社に選ばれていなくても結構評判が立っている企業というのは各地域にあり、「売れている自社製品を持っている」とか「かなり幅広い範囲、遠隔地の顧客がいて、いろいろな加工を頼まれている」という評判で判断することができる。
その2−国の施策を何らかの形で活用している
「補助金を貰ったことがある」とか「国の法律に基づく認定を受けたことがある」といったように、国の施策を何らかの形で活用しているということである。
その3−大学と既に何らかの交渉を持っている
産学連携に関心があり、手を染めているという条件である。
ここまで3条件は、優れたNT型企業、あるいは<揃い踏み企業>のようなGNT企業予備軍までを含めて共通している点を掲げている。問題は、他地域の企業を誘致しようという皆さんには、直接的にはなかなか知りえない情報である可能性が高いことであろう。企業が所在している地域金融機関の方々はこのような情報をかなり持っているので、地域金融機関と組んで教えてもらうといった一工夫が必要かもしれない。また、優れた中小企業支援に当たっている各自治体の支援機関のコーディネーターであれば、この三つの基準に該当しているかどうかは全て分かっているはずである。
その4−従業者一人当たり売上高が1,500万円以上
これはCRDという中小企業の財務状況が分かるデータベースで、ものづくり中小企業全体の中央値(度数分布表を作った時に順番が全企業数の丁度中間に来る企業の値)である。CRDとはクレジット・リスク・データベースの頭文字であり、全国の銀行や信用保証協会などが自分の顧客企業の財務情報を入力したデータベースである、NT型企業の平均は2,000万円弱だったのでそれをはるかに上回っているが、そこまでいかなくても並み以上という意味でこの基準を参考にしてはどうだろうか。従業者一人当たり売上高は、一種の生産性の指標であり、この値が一定以上に達していれば、自社製品の開発など将来に向けた広い意味での投資を行えるだけの企業としての余裕があると考えることができる。
その5−社歴が15年以上
社歴が短すぎるとその企業の業績はなかなか評価しづらい、あるいは別の形で評価しなければならないということになるので、ある程度の事業実績が必要となる。
こういった情報は地域のコーディネーターや金融機関であれば簡単に入手できる。これだけの条件が全て揃っていれば中小ものづくり企業として優良企業と言って間違いはない。