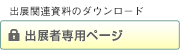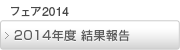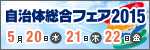わが国人口は、2014年(平成26年)現在で1億2710万人。これが2030年(平成42年)には1億1662万人、2048年(平成60年)には9913万人、そして2060年(平成72年)には8674万人になると見込まれている。このような状況を踏まえ、増田寛也元総務大臣は“地方消滅"で、896市町村が消えるという衝撃的な提起をしている。
一方、2014年度上半期(4〜9月)の貿易収支は5兆4271億円の赤字になった。円安が進んで輸入品の円建て価格が押し上げられたことに加え、火力発電用の液化天然ガス(LNG)の需要が伸びたためだ。輸入が2.5%増の41兆3240億円となる一方、輸出は海外経済の回復が鈍く、1.7%増の35兆8969億円にとどまった。
世界のエネルギー消費量(一次エネルギー)は、経済成長とともに増加を続けており、1965年(昭和40年)の38億toe(tonne of oil equivalent、原油換算トン)から年平均2.6%で増加し続け、2011年(平成23年)は123億toeに達した。
石油は今日までエネルギー消費(一次エネルギー)の中心になってきたが、発電用等では他のエネルギー源への転換もかなり進んできている。石油は、堅調な輸送用燃料消費に支えられ1971年(昭和46年)から2010年(平成22年)にかけて年平均1.3%増加し、依然としてエネルギー消費全体で最も大きなシェア(2010年時点で32.3%)を占めた。
日本の一次エネルギー国内供給は、1965年(昭和40年)から2007年(平成19年)にかけて約3.6倍に増加している。構成割合をみると近年、石油に対する依存の割合が減少し、天然ガスによるエネルギー供給が高まってきている。また化石燃料に比べ二酸化炭素の排出が少ない再生可能エネルギーの重要性が増してきている。
世界の化石燃料の確認埋蔵量は石油40年、天然ガス65年、石炭150年、ウラン85年と言われており、明らかに石炭以外の化石資源は100年以内には枯渇すると言われている。
エネルギーといった場合、一般的に石油、石炭、天然ガスなどを「一次エネルギー」、これらを転換した電気などを「2次エネルギー」と言っている。このような分類では「水素」は、天然ガスの改質や水の電気分解で製造されるものなので2次エネルギーである。
現在は、原子力、石油、天然ガス、石炭火力によって電力が供給されているが、シェールガスの比率が高まっており、電気自動車(EV)も徐々に普及してきている。ここに太陽電池や風力などの話が加わってくるのだが、これらは出力が安定していない。そこで2020年(平成32年)〜2030年(平成42年)には水素ストレージが形成され、大量導入される風力、太陽電池の出力変動を緩和するのに活用されてくるだろう。
現在、家庭の省エネを図るため、エネファーム(家庭用燃料電池・コージェネレーションシステム)の普及が推進されている。エネファームは、ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し、この時発生する熱でお湯を作るもので、従来のエネルギーシステムに比べ高いエネルギー効率を実現している。その発電量は、一般家庭の電気使用量の約7割をカバーできていてトータルの発熱量の削減につながる。価格も昔は700万円もしたものが、今は200万円ほど、将来は50〜60万円位になるだろうから、そうなればものすごいスピードで普及していくことだろう。
ここにきてエネルギーシステムの中で水素が注目されるようになり、エネルギー企業の多くが水素に軸足をおいた「エネルギー変換企業」として、環境に優しく、質の高いエネルギーを供給し続けることで、社会の持続可能な発展に貢献しようとしてきている。
水素は炭素を含まないため、使用過程では地球温暖化の原因となるCO2をまったく発生しないクリーンエネルギーであると同時に、そのほかにもエネルギーとして優れた特性がある。
石油をはじめとした化石燃料は有限である一方、新興国の経済発展、生活レベルの向上によって、今後も石油の需要の拡大が続くと考えられている。そういった社会背景を考慮すると、CO2削減とともに燃料の多様化というものが一層重要になり、電力・水素といった二次エネルギーを有効利用していく必要がある。
これに対し地球上のどこにでも存在する水素は、持続可能な社会を構築する上で大きな可能性を秘めている。CO2フリーの水素がもっと社会に取り込まれ溶け込むようになれば、クリーンな社会が実現できるだろう。
太陽光発電や風力発電は自然条件に左右されるため発電が不安定で、発電コストも高く、得られた電力エネルギーは蓄電池(バッテリー)では自然放電するためいつまでも貯めておくことができないという側面がある。
このような自然エネルギーを使いたい時に使えるエネルギーとして活用するためには、蓄電池より体積エネルギー密度の高い水素に変換して備蓄する方法が効果的である。
蓄電池などの電気グリッドは少量の電気を短期間貯蔵するのには適している。一方、電気で発生させた水素を貯蔵する水素グリッドは、大量の電力を長期間貯蔵したり輸送するのに向いている。
自然エネルギーの先進国ドイツではすでに、北部にある太陽光発電や風力発電で作られた電力を水素に変換し、古くからある岩塩鉱に備蓄したり、既存のパイプラインを利用して南部の各都市に送り利用している。今後の社会は、これから増加すると考えられる再生可能エネルギーの利用に合わせて最適化し、有効に活用していく必要があるはずだ。水素の利用は、スマートエネルギー構想にとっても、高い付加価値を持っている。
太陽光発電の買い取りを電力会社が拒否し始めた、などというニュースを耳にするようになってきたが、太陽光発電や風力発電の電力を安定化させるためには、水素エネルギーに転換し保存していくことが必要だ。燃料電池により電気と熱に変換する方向は、定置型の燃料電池であるエネファームがますます進んでくると思われる。今後は水素供給ネットワークというか、サプライチェーンをどのように構築するかがわが国経済社会の発展にとって重要な課題であるといえよう。また、燃料電池車(FCV)についても、2020年(平成32年)の東京オリンピックまでに、世界的なデファクトスタンダードを取るものと思われる。
ハイブリット車(HEV)にはガソリン車の内燃機関があるので、従来の生産ラインがそのまま必要である。HEVに対して、数年前に表舞台に出てきた電気自動車(EV)は電池とバッテリーだけで走る。FCVは、エンジンに相当する「FCスタック」に電解質膜とセパレーターを数百枚重ねて、ここで水素を化学反応させて発電している。
EVやFCVはHEVに比べ、部品点数が少なく、従来の自動車産業のようにすそ野が広い産業であるとは言いにくい。時計産業におけるゼンマイ時計とクォーツ時計の違いと同じである。
ということは自動車部品工場が周辺から減っていくわけである。これに対してコージェネシステムは部品点数が多い。またエネファームも同様で、普及が進めば、かなり波及効果の高い産業になりそうである。FCV及びエネファームは成長産業であり、新規立地が期待できるが、FCVの方は既存の自動車工場周辺を中心に進むと考えられる。一方、エネファームは、板金加工、機械加工、などが必要とされ、こちらの方は、関連する加工分野も含め、新規立地の可能性が期待できそうである。
冒頭私は、日本の人口は今後減少する、と述べた。これを年齢比率でみると、65歳以上の老年人口は23.3%(2011年)から29.1%(2020年)へと急拡大する。民間設備投資に関しては、今後の生産年齢人口減少および老年人口増加を考慮すると、特定分野(医療等)での新規投資はみられるかもしれないが、日本全体として強力なエンジンになるとは考えにくい。
公共投資については、巨額の財政赤字を抱えるなかで、震災復興投資や老朽化対策など喫緊のものを除けば投資が急増するとも考えにくい。むしろ社会福祉など所得の世代間移転のウェイトが高まることになるだろう。輸出主導で景気を支えているドイツのように、中小企業も含めた層の厚い輸出構造にする必要があるだろう。
日本は海外資産保有大国であり、企業経営で言うところの資産収益率を高めて、いかに日本経済に取り込むかといった視点も重要である。海外資産への依存度を高めることは、それだけグローバル経済の不確実性に良くも悪くもさらされてしまうことになるが、日本国内だけでは事業の大きな発展は難しいことも事実である。
実は日本人は金持ちである。日本全体で総資産2,500兆円程度(国民経済計算年報)、負債を控除した金融の純資産1,000兆円程度(日銀資金循環勘定)ある。
しかも世帯主が60歳以上の家計においては金融資産残高が非常に大きい。彼らの消費支出自体は50代前半をピークに減少するため、消費に及ぼす影響はあまり大きくなさそうである。
このように高資産を有する高齢者市場への対応として、近年高齢者対応の店舗や商品陳列をする百貨店やスーパーが増えつつある。これらの店舗で売られている商品は、簡単にかみ切れるハンバーグや豚の角煮などで、もともと外食や宅配弁当業者に売り出されてきたものだが、今や一般客向けの需要が出てきたというわけである。だからこれからは、シニア市場向けの食品加工センターやロジスティクスセンターが必要になってくる可能性もある。
立地選定時に重視する要件について日本立地センターの「新規事業所計画に関する動向調査」をみてみると、「用地価格」が回答率65.5%で突出していたが、続く要件としては「優遇制度」(23.6%)などよりも、「既存拠点と近接」(41.7%)、「取引先・市場との近接」(24%)等が挙げられている。
海外生産が急激に進んでいるなかで、ここ10年くらい、日本において新たな工場を建設した大手製造業等の例を追跡すると、「既存拠点と近接」という要因が大きいということに辿り着く。近くに主要工場や関連する企業群が集積しているから、というのである。
東京にある拠点研究所や工場を地方の工場に移転するケースも見られる。こうしたことを機に新技術、新商品が出てくることが期待されているようでもある。
また海外生産へと移行したあとの土地に、オープンイノベーションの拠点を構築しようという動きもある。自社のみに偏らず他社とジョイントして新たな戦略商品を開発しようとしているのである。ここで開発された新商品を製作するには、周辺に生産協力会社を探すことになるが地方の開発型企業の中には、十分な実力を持った企業があるので傘下に入ってもらったりすることがある。逆に地方の開発型企業自身が、新たな事業環境を構築するために、新規に工場を建てたり、既存の工場を改装したりする工場が出てきている。
一般財団法人日本立地センター松崎研究員の「都道府県の企業誘致活動について」2014年(平成26年)3月産業立地によると、企業誘致のために最近5年間で最も効果の高かった施策は、「税制・補助金の優遇制度」が挙がっている、と述べている。企業誘致活動の重要性は、今後も変わらないと思うし、かつ「税制・補助金の優遇制度」が重要であることは理解できる。しかし、予算のかけ方や補助金額の大小があろうとも、今日ではほぼ出そろった感が拭えない。
誘致する側はこれしか出せない、と言うし、企業は補助金とかの問題ではない、と言う。そうしたことではなく、拠点としての環境をどう整えるか、になってきているのだろう。
誘致する側は電力の安定供給というニーズに対応して、今後のエネルギー革命の動向など新たな動きにどう感度を高めるか。エネルギーが水素に変わるかもしれない、というのであれば、水素がどう動くのか、水素を巡ってどの企業がどう動くのかに注目していかなければならない。
誘致した大企業や自らの地域にある開発型や技術集約型の中小企業に新たな事業の芽がないか、そしてそれがオープンイノベーションの潮流の中の芽になるような仕組みや仕掛けも必要になると考えられる。
そのような中から、新たなデファクトスタンダードが生まれ日本経済の活性化の一助になってくれることを望んでいることにも注目していく必要がある。
こうした見方をしていくと、東日本大震災で被災した気仙沼の企業からは学ぶもの、見習うべきことが多い。バイオマス熱供給プロジェクトなど先取りするテーマを、逆境をばねに取り込んでいる、と思わずにはいられないのである。