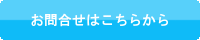人事制度
人事制度は人事に関するさまざまな制度の総合体です。代表的な制度として次のような制度があります。
| 1) |
採用管理制度 |
2) |
定員管理制度 |
3) |
人材配置 |
| 4) |
服務管理 |
5) |
人事考課(評価)制度 |
6) |
職務等級制度・能力等級制度 |
| 7) |
目標管理制度(MBO) |
8) |
複線型人事制度 |
9) |
給与制度 |
| 10) |
昇任・昇格制度 |
11) |
人事異動システム |
12) |
小集団活動 |
| 13) |
提案制度 |
14) |
多面評価制度 |
15) |
自己申告制度 |
| 16) |
役職任期制度・役職定年制度 |
17) |
管理職公募制度 |
18) |
キャリアディベロップメントプログラム(CDP) |
| 19) |
OJT・OffJT |
20) |
退職勧奨制度 |
21) |
再任用制度 |
| 22) |
庁内(人材)公募制度 |
23) |
庁内FA制度 |
24) |
メンター制度・逆メンター制度 |
| 25) |
外部機関派遣制度 等 |
|
|
|
|
これらの制度はそれぞれ関連していますので、新たに制度を導入する場合や制度を変更する場合は関連性に十分留意する必要があります。
これら各種制度の中で、とくに柱となり、重要と考えられるものを次の図に示します。それぞれは密接に関連しますので、設計に際しては十分留意する必要があります。
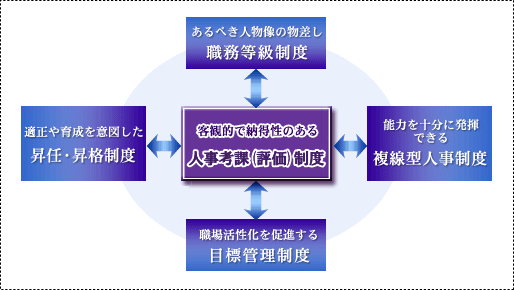
人事考課(評価)制度
人事考課(評価)は、勤務評定といわれることもあります。勤務評定という言葉には、被考課(評価)者に格差を付ける査定主義という意味合いがあるように感じられる方も多 いのではないかと思われます。勤務評定は、部下の管理指導をそれぞれの管理監督者に任せると、各人が思いのままに観察や指導を行い、組織的に部下 を育成していくことに問題が生じたために、一定の時期に、一定の方法で「部下の観察をどのようにしているか」、「部下の指導をどのようにしているか」と いったことを文書で報告させることによって、こうした問題を回避しようとしたことが、その出発点ともいわれています。
これに対して、人事考課(評価)は被考課(評価)者に格差を付けることを目的として実施するのではなく、それぞれの職員の長所や短所などを把握して、個人の特性に応じた育成等を進めるために実施するものです。
人事考課(評価)制度の導入は基本として次の4ステップで行います。
| 内容 |
方法等 |
|
導入検討段階
|
研究会 |
| 次のような内容を理解します。 |
勉強会 など |
| (1)人事考課(評価)制度の考え方 |
|
| (2)「評価する(される)」とはどういうことなのか |
期間:1~2ヶ月 |
| (3)他の自治体の事例研究 |
|
| (4)人事考課(評価)の必要性と課題 |
|

第2ステップ
| 内容 |
方法等 |
|
人事考課(評価)制度設計段階
|
ヒアリング |
| 次のような内容を指導していきます(一例です)。 |
庁内プロジェクト指導 |
| (1)前提条件の明確化(・検討方針やスケジュールの設定・導入目標の明確化等) |
アンケート調査 |
| (2)考課(評価)基準の設定(・人物像の想定・考課(評価)要素の検討・考課(評価)項目の設定等) |
|
| (3)考課(評価)票の作成(・考課(評価)項目ウェイト設定・考課(評価)区分ごとの考課(評価)票作成等) |
期間:2~4ヶ月 |

第3ステップ
| 内容 |
方法等 |
|
本格導入段階
|
トップへのプレゼン |
| 次のような内容を指導していきます(一例です)。 |
庁内プロジェクト指導 |
| (1)実用性の検証 |
トライアル実施の支援 |
| (2)トライアル実施 |
|
| (3)考課(評価)精度向上のための各種支援 |
期間:2~4ヶ月 |
| (4)規程類の整備 |
|
| (5)マニュアルの整備 |

第4ステップ
| 内容 |
方法等 |
|
導入前最終検討段階
|
結果の分析 |
| 次のような内容を指導していきます(一例です)。 |
各種支援 |
| (1)業務特性に基づく考課(評価)のフォロー |
|
| (2)業務ごとのケーススタディの作成 |
|
| (3)考課(評価)者研修(被考課(評価)者研修) |
|
| (4)定着に向けてのフォロー |
|
| (5)考課(評価)者研修の継続 |
地方自治体での検討状況などにより、どのステップからでも入ることができます。
なお、期間については目安ですので正式な企画書等で提示する期間とは異なることがあります。
目標管理制度(MBO)
目標による管理制度(MBO)は、職員一人ひとりが自分の職務目標を明確に掲げて職務遂行にあたるもので、実施にあたっては上司が部下に対して組織の年間目標
と課題を説明し、これを受けて部下は半年あるいは1年間の仕事上の目標を定量的・定性的両面から、できるだけ具体的にたてます。
そしてこれを、目標管理シートに明示化します。(一般に目標管理シートの内容は、今期の重点目標、 目標達成のための具体的手段・方策、目標達成度についての自己評価(期末評価時に記入)、目標達成に関する上司の所見等からなります。)目標管理シートの作成ではトップダウンとボトムアップを行うところに特徴があります。
目標管理の最大の特長は、「目標設定への参画」と「自己統制」にあります。「目標設定への参画」とは、職員自らが自発的に目標を設定することをいい、上司の指示命令によってではなく自主的に目標設定に取り組みます。したがって、部下の自主性を認めない「目標管理」や「ノルマによる管理」は、目標管理とはいえません。
具体的な内容と手順をステップごとに示すと以下のようになります。
第1ステップ
上司が部下に対して組織の年間全体目標や部門組織の年間目標を説明します。これを受けた部下は、半年あるいは1年間の仕事上の目標を定量的・定性的両面からできるだけ具体的にたてます。

第2ステップ
個人目標について上司と話し合い、個人の期間目標を設定し文書にて明示化します。

第3ステップ
職員は自分で立てた目標の遂行に向けて、自律的に挑戦します。その間、上司は部下の業務進捗状況を確認したり意見交換を行う等により、支援します。

第4ステップ
期末になると部下は達成状況等を自己評価し、これを上司と話し合って上司が評価します。評価結果自体は制度導入の目的に照らして活用します。
人材育成基本方針策定・見直し、人材育成計画の策定・見直し
地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化、情報化、景気の低迷、グローバル化の進展等々により大きく変化しており、これに伴って住民生活や住民ニーズも大きく変わってきています。これを受け、自治体が抱える行政課題も大きく変化しており、自治体はその組織風土や職員意識を変えることが求められるようになっています。
人材育成基本方針の策定・見直しに当たっては、良質な住民サービスを提供するための人材育成ニーズや組織風土状況を明らかにし、その上で人材育成基本方針を策定するものとして、組織の活性度の状況、業務へのインセンティブ、リーダーシップの状況、研修、OJTの状況等を調査し、課題を抽出します。その後、今後の方向性について、団体の基本的な考え方を確認し、人事諸制度と能力開発、研修体系等の関連性も明確にした上で、人材育成基本方針を策定します。
なお、人材育成基本方針の策定においては、職員の自律性のある行動変革と能力開発を促し、経営感覚に優れた職員を育成する観点から、職場風土の改善の他、人事制度の見直しについても検討を行います。このため、策定・見直しでは団体内にプロジェクトチームを設けていただき、これに対する協議等を通じて策定する方式を基本とします。
また、人材育成計画の策定・見直しでは、人材育成基本方針等を踏まえて、そして必要な場合は職員意識調査を実施し人材育成に関する問題抽出・整理・分析を行ったうえで、課題解決のための実効性ある計画を協議等を進めるなかで策定する方式を基本とします。